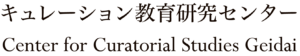東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクト2024
(東京藝大×〈みずほ〉「アートとジェンダー」共同研究プロジェクト)
採択企画レポート
さまざまな環境の子どもたちに、伝統芸能を届ける工夫
キュレーション教育研究センター(CCS)とみずほフィナンシャルグループは、本学卒業生・修了生対象の企画公募事業「I LOVE YOU」プロジェクト2024を共同で実施しております。
本レポートでは、2024年度に採択した企画のひとつ「児童養護施設での狂言ワークショップ」について、企画内容から実施の様子について報告します。
企画概要
タイトル:児童養護施設での狂言ワークショップ
内容:児童養護施設にて、狂言ワークショップを実施しました。全4回のシリーズプログラムで実施し、最終回には仮設の能舞台を会場内に設置し、狂言師による演目を鑑賞しました。
会場は都内の児童養護施設に協力いただきました。
各回の実施概要
12月14日 第1回 狂言についておはなしするよ
2月22日 第2回 衣装をきてみよう、踊りをやってみよう
3月1日 第3回 お芝居をやってみよう
3月15日 狂言「梟山伏」をみよう 質問コーナー
企画者である野村拳之介(のむら けんのすけ)さんは、音楽学部能楽専攻を卒業後、現在は狂言師として国内外のさまざまな舞台に立っています。彼が企画した「児童養護施設での狂言ワークショップ」は、狂言の演技や衣装の着用体験のほか、児童養護施設内に仮設の能舞台を設置し、最後にプロの狂言師による演目を鑑賞するという内容でした。
実施先を児童養護施設に選定した理由には、これまで実施した経験がないこと、また文化的体験の格差を解消したいとの野村さんの思いがありました。野村さんご自身は、普段から学校等へのアウトリーチを行っている実績がある一方、児童養護施設での開催は初めて。普段の実施場所とは異なる環境、また複雑な背景を持つ子どもたちとともに、どのようなワークショップが可能かが大きな課題でした。
実施に向けて
6月の採択後、CCSスタッフと野村さん、みずほメンターの3者でミーティングを開催。会場となる児童養護施設の想定はあるか、これまでのワークショップ経験などのヒアリングを行いました。そこで、会場となる児童養護施設への打診はCCSスタッフが引き受けること、また1日限りのイベントにするのではなく、何度か施設へ通い子どもたちと関係性を構築するプログラムへ組み直すことが決まりました。8月には実施先の児童養護施設が決定。施設の担当者は、打ち合わせで狂言ワークショップの開催に好意的な反応を示してくれました。調整の結果、12月から3月にかけて全4回の狂言ワークショップを実施することが決まりました。
実施に向けて、再度野村さんとCCSスタッフ、みずほメンターも含めたミーティングを実施。ワークショップの内容や準備について打ち合わせを行いました。児童養護施設で、どのように子どもたちに接するか、CCSスタッフやみずほメンターからは心配する声が上がりましたが、盲学校などでもワークショップ経験がある野村さんは「こういう子だからと決めつけずに、その場で出会った子たちと向き合うことを大切にしたい」と語りました。

CCS、みずほメンターとのミーティングの様子
12月14日 第1回目のワークショップ
このワークショップでは参加する子どもたちとの顔合わせを主な目的とし、自己紹介と簡単な狂言の説明を行いました。初回のワークショップには、計2名が参加しました。子どもの人数に対して視察や施設の職員含め、大人は7名以上という大所帯。大人の視線が気になる中でのワークショップとなり、参加した子どもたちは、会場の後ろにかたまる大人たちをチラチラ振り返りながらの参加になってしまいました。
自己紹介ののち、狂言についての説明を始めた野村さん。「狂言は600年前のお笑い」と伝えても、子どもたちはピンときていない様子です。そこで切り替え、狂言の小道具である扇を取り出しました。すると「なにそれ」と子どもたちが野村さんの近くに寄っていきます。扇を使い、狂言の演目ででてくる酒を注ぐしぐさを実演してみせます。「ドブドブドブ」と言いながら、開いた扇を徐々に上にあげ、お酒を注ぐ演技をする野村さん。聞きなれないオノマトペと、大きな振る舞いに、子どもたちは大笑い。あっという間に狂言の世界に引き込まれていました。続いて、閉じた扇を刀に見立て、鞘から刀を抜き、相手を斬る演技を子どもたちと一緒にやってみます。
最後は狂言に出てくる生き物クイズをしました。野村さんが狂言に出てくる生き物の演技をみせ、子どもたちが何の動物か当てます。こちらも大盛り上がり。とりわけ、キノコの精が移動する独特な歩き方で、子どもたちは魅了されていました。
2月22日 第2回目ワークショップ
この日は狂言の衣装を身に着けてもらう衣装体験と、舞いを体験しました。1回目の実施から2ヶ月ほど時間が経ってしまったため、子どもたちが継続して参加してくれるか不安でしたが、初回に参加してくれた2名に加え、新しく2名も参加し、計4名での実施となりました。
45分という短いワークショップの時間内に、衣装の着付けと、舞いの体験をするため、かなりタイトなスケジュールとなりました。衣装を身に着けると背筋が伸びる子どもたち。立ち方、歩き方、座り方など、基本的な振る舞いを一緒にやってみます。また、後半の約10分で、狂言に登場する唄と舞いも体験。盛りだくさんな内容となりました。最後は子どもたちから「キノコやって~!」とリクエストが。野村さんと子どもたちがキノコの動きをしながら、参加者対抗キノコレースが開幕されました。
3月1日 第3回ワークショップ
第3回目のワークショップでは、初回と第2回目に参加した2名、そして、第2回目に初参加した1名の計3名が参加しました。このワークショップでは、狂言に出てくる感情表現を一緒に実演してみます。笑い、泣き、怒りなど、狂言特有の擬音語や身体表現を、まずは野村さんが実演。大きな声や誇張表現を目の前で見て、その迫力にはじめは驚いた様子の子どもたちでしたが、一緒に声を出していくことで、次第にこわばりも解けていきました。
ワークショップ終了時には、「つぎはいつ来るの?」と子どもたちからの問いかけが。「2週間後、それが最終回だよ」と伝えると、「えー予定があって行けないや。その後は来ないの?」と会話が続きました。
3月15日 最終回
最終回は児童養護施設内に仮設の能舞台を設置し、「梟山伏」を鑑賞します。あいにく初回から第3回目まで来てくれていた2名は予定があり不参加でしたが、第2回目から継続して参加している1名の子どもが最終日も参加し、また演目を鑑賞しに幼児クラスの子どもたち3名も参加してくれました。これまでワークショップを行ってきた会場を半分に区切り、能舞台の松が描かれた鏡板がプリントされたスクリーンを背景に設置し、舞台を養生テープで区切って舞台を立ち上がらせます。演目前にこれまでのワークショップのおさらいと、今回の演目のあらすじの説明を行いました。初めてワークショップに参加する子どもたちにとっては、大きな声や身振り、低い声がかなり怖かった様子。それでも、驚き飛びのく、慌てふためくなど、コミカルな動きには反応して、大笑いしていました。

「梟山伏」参考画像(提供:萬狂言)
終演後は野村さんと参加してくれた子どもたちで、感想や質問をやり取り。第2回目から継続参加している子どもが、衣装のや演目のあらすじについて、細かく野村さんに質問をしている様子が印象的でした。
普段からさまざまな教育機関や団体で狂言ワークショップを行っている野村さん。そのため子どもたちの関心を引き付ける数々の工夫をこらしてワークショップを行っていました。今後は今回の経験をもとに、参加した子どもたち一人ひとりの個性に向き合うワークショップへの発展を期待しています。
現代美術とは違い、しっかりした型がある伝統文化の世界。長い時間をかけて磨かれた芸は、一瞬にして人々を惹き付ける強い力をもっています。そのパワーを活かし、実施場所や向き合う子どもたちに合わせて、ワークショップの内容や形式を変化させていく柔軟さが必要だと感じました。
文:屋宜初音