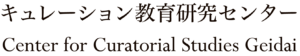これからの「キュレーション」とは何か
ーキュレーション教育研究センターの役割と展望
2024年11月30日(土)に、東京藝術大学大学美術館で行われた「芸術未来研究場展*注」の関連イベントとして、キュレーション教育研究センター(以下、CCS)のミニトークが開催されました。ミニトークでは、センター長の今村有策、副センター長の熊倉純子、特任准教授の難波祐子の3名が、CCSの掲げる「キュレーション」やセンターの役割について話し合いました。本レポートでは、ミニトークの内容を報告します。
文=韓河羅(CCS特任助教)
■開催概要
CCSミニトーク
日時:2024年11月30日(土)16:15〜16:45
会場:東京藝術大学 上野キャンパス 音楽学部 5-109
料金:無料(先着順、予約不要)
登壇者:今村有策(東京藝術大学副学長/CCSセンター長)、熊倉純子(東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科長/CCS副センター長)、難波祐子(CCS特任准教授)
主催:東京藝術大学キュレーション教育研究センター
HP:https://ccs.geidai.ac.jp/2024/11/07/ccsgmk/
――はじめに
2023年度から本格始動した「キュレーション教育研究センター(以下、CCS)」。 そもそも「キュレーション」とは何を指し示す言葉なのでしょうか。今村センター長はトークの冒頭で、「『キュレーション』とは日本的造語です。欧米圏では通常『キュレーティング(curating)』や『キュレトリアル・スタディーズ(Curatorial Studies)』という言葉が使われています。だからこそ、『キュレーション』という新しい言葉には可能性が秘められていると言えるのではないか」と提起しました。
東京藝術大学(以下、東京藝大)では、2023年4月より、「人が生きる力であるアートを根幹に据え、人類と地球のあるべき姿を探求するための組織」として「芸術未来研究場」が創設されました。6つの領域からなる「芸術未来研究場」のうち、CCSはキュレーション領域を担う組織として位置づけられています。
今村センター長は、芸術未来研究場の「未来」というキーワードに着目し、「東日本大震災後も現地で活動をしてきましたが、個人的な経験として、未来という希望がなければ人間は次に向かって踏み出せないと実感しています。CCSとして、どのような次なる希望を『キュレーション』に見出していくかというところに取り組んでいきたい」と語ります。

――卒業・修了後に期待されるキュレーション力
キュレーションへの今村センター長の思いに賛同し、CCSの共同発起人となった熊倉副センター長は、東京藝大の教育の課題を次のように指摘します。
「東京藝大は美術家を育てて135年、演奏家を育てて134年になります**注。つまり、生産する人材を輩出する教育が今でも主軸です。しかし、卒業・修了後に全員がアーティストになれるわけではありません。統計をとっているわけではありませんが、作品を売って食べていける人は決して多くはありません。同様に、演奏活動で生計を立てていく人も一握りでしょう。一方で、表現行為というものに実践的に携わった経験を活かして、卒業・修了後はアーティストと社会をつなぐ仕事に就いている人のほうが多いのではないかと感じています。」
在学中の藝大生は、第一線のアートの現場で活躍するアーティストや研究者の先生から、表現行為を磨くさまざまな技術や知識、心構えなどを学んでいます。しかし、卒業・修了後には、他分野や社会全般とアートの間を翻訳するキュレーション力やマネジメント力こそが、社会から期待されている役割なのではないかと熊倉副センター長は見解を述べました。
また、本学は学部から大学院まで、ひとつの表現を極めることが推奨される教育環境であるという特徴があります。その点について熊倉副センター長は「メリットとデメリットがある」とした上で、ある種タコつぼ化している環境を打破するべく、学内のさまざまな専門性を活かした領域横断的な学びの機会をつくるために「芸術未来研究場」が設立されたと強調します。
――学内外のハブとしてのCCS
そこで、CCSが試みているのが、学内外を繋げるハブとなるような社会的実践の場です。すべての藝大生が、社会と繋がる術や大学の外で体系的に実践する経験に触れられる場を開けないか。そのような思いを出発点にして、CCS独自の授業と事業を展開しています。
「教育」に関する試みとしては、2023年より開講した「社会共創科目(公開授業)」があります。東京藝大初の試みである「社会共創科目」は、学内向けの正規科目を学外の方々も受講できるというものです。座学のほかにも、「展覧会設計演習」といった実践的な科目もあり、藝大生と社会人とがともに学ぶ科目となっています。
CCSのもうひとつの軸である「研究」については、現在、みずほフィナンシャルグループと「アートとジェンダー」共同研究を実施しています。「アートとジェンダー」というテーマに関しては、東京藝大の男女比率の課題を発端としています。在学生の約70%が女性である一方で、女性教員の割合は約20%に留まるというアンバランスな現状が横たわっています。そんな中で、女性の若き表現者やアートと社会をつなぐ術を学ぶ学生たちは、どのような問題意識を持っているのか。あるいは、社会に出たときに、どのような課題が待ち構えているのかということを、みずほ社員とともにさまざまな角度から実践・研究しています。

――なんでもありの現代美術をキュレーションする
キュレーターとして活躍する難波特任准教授は、キュレーションのなかでも「現代美術のキュレーション」をテーマに、CCSでさまざまな科目やプロジェクトを担当されています。ミニトークでは、「現代美術」と「キュレーション」のそれぞれの言葉が持つ意味について紹介されました。
難波特任准教授は、現代美術とは「良くも悪くもなんでもあり」として、だからこそ「懐の深いメディアでもある」と述べます。美術が取り扱う領域と言えば、絵画や彫刻といったイメージがあるかもしれません。しかし今では、インスタレーション、映像、パフォーマンス、建築、デザインも美術で取り扱われる領域となっており、さらには参加型のプロジェクトといった形に残らないものも現代美術に含まれることがあります。また、現代美術はファインアート(純粋芸術)の文脈に留まることなく、福祉や地域社会、科学といった他領域との協働も活発であり、さまざまな要素と絡み合いながら成り立つのが「現代美術」の現在地となっています。
さて、「キュレーション」という言葉に立ち返ると、その語源はラテン語の「curare(世話する、治療する)」にあります。その言葉が転じて、博物館や美術館の所蔵品の管理者という意味が定着し、狭義の意味で、展覧会の企画を行う者として「キュレーター」という言葉が用いられるようになりました。「2000年代前半は、オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー(英語圏で権威ある英語辞典)に『キュレーター』の定義は載っていなかった」と難波特任准教授が振り返るように、キュレーターとは欧米圏でも比較的新しい職能です。
以上を踏まえて、難波特任准教授は「アーティストを取り巻く『アート』とわたしたちを取り巻く『社会』を繋ぐ言説と実践が『キュレーション』である」と簡潔にまとめます。現代美術は美術的な文脈に限らず、現代の様々な課題に向き合う異なる領域にも通じています。つまり、「現代美術のキュレーション」とは、美術館という環境だけでなく、そのコレクション形成や地域コミュニティとの協働など、絡み合う文脈を横断的に繋ぎ、ありとあらゆる知識とスキルを組み合わせて新しい言説をつくる技と言えます。
「キュレーション」だけでなく「キュレーター」もまた、定義が定まっていない言葉ですが、そのことをポジティブに捉えてキュレーターの役割を拡張していくことがCCSの活動における一つの軸になっています。

――感性の術で、カオスを共有する場を仕掛ける
CCSの目的や現代美術のキュレーションといったトピックを踏まえて、今村センター長はこれからの大学のあり方についても話題を広げます。今村センター長は「アートは生きるためのテクノロジー」であるとした上で、「いわゆる『教えるだけの大学』では時代のニーズには答えられなくなっている中で、新たな希望や生きるためのテクノロジーを協働で考える場として『芸術未来研究場』があると自分は解釈しています」と独自の見解を述べました。
一方で、学内外を横断する構想として立ち上がった「芸術未来研究場」ですが、6領域に分類されていることで「すでにセグメント化が起こっている」と今村センター長は指摘します。そこで、CCSがそれぞれの領域を繋ぎ、「東京藝大の中にある面白いカオス」を共有する場や、そのような場をつくることを率先して負うことが重要だと強調します。CCSが最終的に目指すのは、すでに価値があると決められた作品を展覧会で提示することではなく、価値そのものや価値とは何かを共有する場を仕掛けることであり、それこそが本質的な「キュレーション」なのではないかと今村センター長は投げかけました。
これに対し熊倉副センター長は、キュレーションを「感性の術」だと捉え直すことを提案します。産業革命以降、マジョリティが資本主義を推し進めてきた結果、利益や合理性という価値軸から感性がするすると抜け落ちてきたことが、今日の社会の歪な構造を加速化させているのではないか。熊倉副センター長は、CCSの開設科目への反響や共同研究での実感を通じて、そのような警鐘を無意識に受け取っている人が少なくないと言います。それだけ、現状を打破するヒントが「感性の術」にあると感じている人が着実に増えているのかもしれません。
さらに熊倉副センター長は「CCSが掲げる『キュレーション』は美術だけでなく音楽においても重要なアプローチ」と異なる視点を付け加えました。音楽は目に見えませんが、楽曲や楽譜を第一とするモノ中心の世界でもあり、そのような意味では音楽分野と美術分野は同じ傾向を持っているとも捉えられます。熊倉副センター長は「美術に限らずパフォーミングアーツも、モノをコト化して社会を違う角度からケアすることがまさに求められている」と喚起します。また、難波特任准教授は「アートは『わからなさ』の媒介になる」とアートの効能を挙げました。わからなさや感性を扱うやりかたのノウハウはありません。だからこそ、違う分野で社会をケアしている人々と手を携えて一緒に考えていく余白がそこにはあるとも言えるのです。
――おわりに
最後に、今村センター長は「教育研究センター」としてのCCSのあり方を次のように再考します。「長らく大学はプロフェッショナルの輩出を目指してきました。しかし、ジェネラリストをもう一度つくらないといけないという時代に来ているのかなと感じています。」
新たなわからなさや答えのないものを、開かれた視野で一緒に考えることのできる場がますます求められる一方で、そのような場を設える人材は常に不足しています。そこで、アートと社会を繋ぐジェネラリスト的な人材の育成に、CCSが寄与できればという期待が寄せられました。


「芸術未来研究場展」
会期:2024年11月27日(水)〜12月3日(火)
開館時間:10:00〜17:00(入館は会館の30分前まで)
会場:東京藝術大学大学美術館本館3F 展示室3・4ほか
観覧無料・申込不要
会期中休館なし
HP:https://museum.geidai.ac.jp/exhibit/2024/11/gmk2024.html
主催:東京藝術大学 芸術未来研究場、共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点(ケア&コミュニケーション領域)
協力:東京藝術大学大学美術館
開催概要:芸術未来研究場に位置づけられている6領域の活動を一堂に紹介した展覧会。会期中はさまざまなイベントやワークショップが開かれ、約3000人が来場しました。
*注
「芸術未来研究場」
本学は、アートの礎である「いまここにないものをイメージする力」をもとに、伝統の継承と新しい表現の創造のための教育研究機関であると同時に、様々なステークホルダーと共に社会を形づくる主体を目指し、2023年4月に「芸術未来研究場」を設置しました。日比野克彦学長が打ち出した「芸術未来研究場」は、全学横断的に企業・官公庁・他の教育研究機関との連携を強化/推進する新たなプラットフォームとして6つの領域実践:[ケア・コミュニケーション][アートDX][クリエイティヴアーカイヴ][キュレーション][芸術教育・リベラルアーツ][アート×ビジネス]を据えています。CCSはこのうちの[キュレーション]領域を担う組織として、特に期待が寄せられています。
参照:https://geidai-park.geidai.ac.jp/
**注
東京藝大の前身である東京美術学校(1889年開校)および東京音楽学校(1890年開校)の開校年を基準とした場合。(参照:<a href=”https://www.geidai.ac.jp/outline/introduction/history” target=”_blank” rel=”noopener”>https://www.geidai.ac.jp/outline/introduction/history</a>)